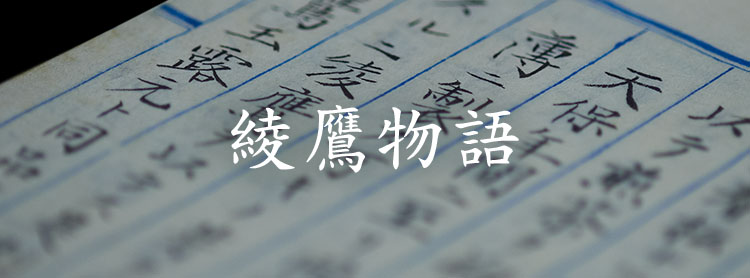今日の煎茶ができるまで
- 宇治の「天下一の茶」は碾茶(てんちゃ)
-

宇治市内覆下園
私たちが日ごろ慣れ親しんでいる煎茶は、江戸時代の中頃、永谷宗円(そうえん)によって完成されました。
戦国時代の初めに「天下一の茶」として愛されるようになった宇治の茶は、「覆下(おおいした)栽培」によって生産された茶葉を摘み取り、これらを蒸して作った碾茶(てんちゃ:抹茶のもととなる茶葉)でした。覆下栽培とは、茶樹を藁(わら)束や莚(むしろ)などで覆って育てる栽培方法で、「被覆(ひふく)栽培」ともいわれています。日光を遮ることによって、茶の旨み成分であるテアニンのカテキンへの転換を抑え、渋味の少ない旨み豊かな茶葉を栽培することができます。また、寒風や霜を防いで新芽が硬葉(こわば)になるのを遅らせることにより、柔らかく色鮮やかな茶葉を育てることができます。宇治のお茶は、このような栽培方法で育てられた茶葉を使用して作られていました。
- 庶民が飲んでいた煎茶とは
-

隠元禅師(萬福寺蔵)
この宇治の覆下栽培による碾茶(てんちゃ)は、抹茶の原料として将軍家や大名家に代表される当時の上流階級に愛好されました。しかし、覆下栽培は宇治の「御茶師三仲ヶ間(さんなかま)」にしか認められていませんでした。そこで、戦国時代から江戸時代にかけた庶民向けのお茶は、覆いをしない露天園で栽培されたものでした。
一般庶民のあいだで飲まれていたお茶は、茶葉を若葉・古葉の区別なく摘み取り、灰のアクを加えた熱湯でゆがき、冷水で冷やしたあとに乾かして煎じたものでした。また、その水色は茶色で、今日の煎茶とは色、味、香気ともにかなり異なるものでした。江戸幕府4代将軍徳川家綱の時代の万治3年(1660年)には、長崎・興福寺の僧に招かれて禅僧の隠元(いんげん)が明から渡来しました。インゲン豆を日本にもたらしたことでも知られる隠元は、自ら宇治に開山した萬福寺で唐茶を作り、お茶の普及に貢献します。唐茶は、茶葉を蒸すのではなく、鍋か釜に入れて揉みながら炒った釜炒り茶でした。一部の人たちに愛用されましたが、唐茶の味わいは強く、日本人向きではなかったようです。
- 永谷宗円、新しい煎茶の製法を考案
-

上:永谷宗円(妙楽寺蔵)
そうした中、永谷宗円が現在のお茶の基礎となる煎茶を考案します。
宗円は、山城国の宇治田原郷(現在の京都府綴喜郡(つづきぐん)宇治田原町)の製茶業を営む家に生まれます。家業の製茶業を引き継いだ宗円は、研究を重ね、元文3年(1738年)に新しい煎茶の製法を考案しました。
その製法とは、新芽だけを用いて湯で蒸したあとに冷却し、焙炉(ほいろ)で乾燥させたものを煎じて飲むというものでした。それまでの煎茶の製法を改良し、宇治の碾茶(抹茶)の製法や、隠元の唐茶で知られた釜炒り茶の製法を取り入れながら考え出された製法でした。お茶は新芽を蒸すことによって美しい薄緑色になり、従来の煎茶より味・香りともに格段によいお茶が誕生したのです。
- 「青製」や「宇治製」として全国に
-
宗円は、この新しい製法による煎茶を携えて江戸へ向かい、江戸日本橋の茶商・山本嘉兵衛(かへい)に販売を依頼します。茶商は茶師とは違い、茶を仕入れて一般に販売する家業で、嘉兵衛はその香味を絶賛し、「天下一」の茶銘で大々的に売り出して好評を博します。
取引はその後も永く続き、山本家は永谷家に明治8年(1875年)に至るまで毎年25両の小判を贈り、その功労に酬いたと伝えられています。
永谷宗円が考案した画期的な製法は、その茶葉の色から「青製」や「宇治製」と呼ばれるようになって全国に広まりました。その後、宗円の子孫のひとりが「永谷園」を創業、また茶商・山本嘉兵衛が創業した「山本山」は日本橋で商いを続け、今もその名が知られています。
- 「茶師」と「茶商」
- 上林春松家は宇治を代表する「茶師」として代々茶業を営んできました。茶師は、抹茶の原料となる碾茶(てんちゃ)の製造家のことをいい、中でも宇治の茶師は、朝廷や幕府の御用茶を製造して納入するという、格式のある特別な職務を担っていました。茶師の仕事は、吟味した茶葉それぞれの特徴を生かしながら組み合わせ、より美味しいお茶を仕上げることを特徴としています。一方、山本嘉兵衛などに代表される「茶商」は、各産地の茶農家から茶を仕入れて販売することを主な仕事としていました。
【参考文献】
『茶大百科I 歴史・文化/品質・機能性/品種/製茶』(2008年発行/農山漁村文化協会)
『宇治茶の文化史』(1993年発行/宇治文庫4・宇治市歴史資料館)
『宇治市史 3 近世の歴史と景観』(1976年発行・宇治市)
『緑茶の事典』(日本茶業中央会 監修・改訂3版・2005年発行/柴田書店)
『日本茶のすべてがわかる本 日本茶検定公式テキスト』(日本茶検定委員会 監修・2009年発行/農山漁村文化協会)